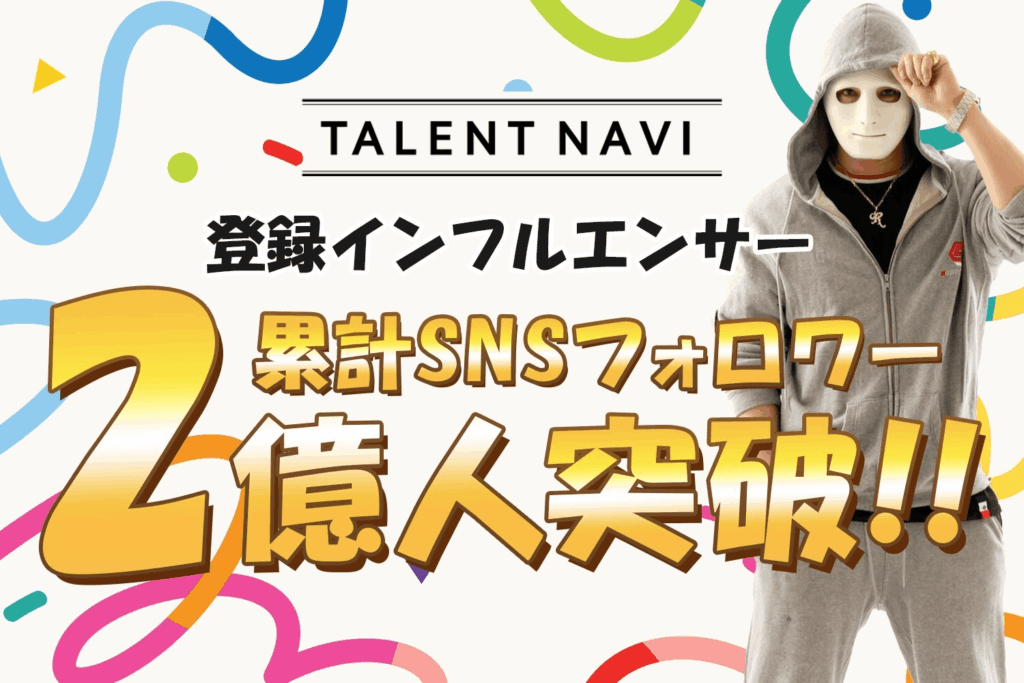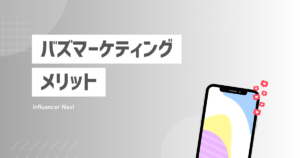インフルエンサーマーケティングは意味ない?問題点を徹底解説!

インフルエンサーマーケティングとは、影響力のあるインフルエンサーを通して商品やサービスを紹介してもらって、直接お客さんの購買行動に繋げる戦略のことです。
SNSがめちゃくちゃ普及してきたおかげで、昔ながらの広告よりも、個人の声の方が重視されるようになってきました。インフルエンサーの人たちが、実際に使ってみた感想とか、おすすめポイントを伝えることで、お客さんの購入意欲が高まります。
一方で、市場が成熟するにつれて、インフルエンサーのPR効果にも陰りが見え始めてるのは事実です。
そこで本記事では、インフルエンサーマーケティングの今の状況と課題、それに効果の測定方法、さらには今後どんな風に進化していくのかについてまとめました。
インフルエンサーマーケティングとは

インフルエンサーマーケティングとは、影響力のあるインフルエンサーを通して自社の商品やサービスを紹介してもらって、ユーザーの購入や問い合わせに繋げるマーケティングの手法のこと
インフルエンサーマーケは、従来の広告方法と比べて、共感を呼びやすく、訴求力が高いと言われています。
特にSNSを使ったマーケティングでは、インフルエンサーのフォロワーとの信頼関係を土台にして、口コミやユーザー生成コンテンツ(UGC)による自然な拡散が期待できます。
上記によって、リーチやエンゲージメントが従来の広告よりもぐっと高まるのが一般的です。マーケティング関連の企業がたくさん調査していますが、SNSマーケティング市場は年々大きくなってることが分かっています。
つまり、消費者が実際に使ってる人の意見や経験を重視して、それを基に購入を決める傾向があることを意味します。
インフルエンサーマーケティングは意味ない?
結論、インフルエンサーマーケティングに効果がないとは言い切れませんが、目的によっては効果を実感できないケースもあると思います。
実際、数年前と比べるとインフルエンサーマーケティングのPR効果は減ってきている調査結果も報告されているし、私が実際に運用しているなかでも感じます。
インフルエンサーのPRの効果が下がってる理由として、いくつかポイントを紹介します。
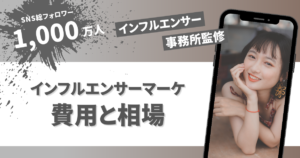
市場が飽和傾向
まず、インフルエンサーマーケティングが当たり前の広告手法として定着したから、市場が飽和状態にあることです。
多くのインフルエンサーが同じような内容を投稿することが増えて、消費者はそれに慣れちゃって新鮮さを感じなくなってきている傾向にあることは否めません。
消費者がインフルエンサーを嫌う
それに、消費者の中には、インフルエンサーが自分の利益のためだけに活動してると感じる人も増えています。
SNSで「インフルエンサーの投稿って全部スポンサーからの案件に見える」みたいな声がたくさん上がってるのを見ても明らかです。
インフルエンサーマーケティングの問題点
【インフルエンサーマーケティングの問題点】
- 市場が飽和状態
- 投稿内容に一貫性がない
- 消費者からの反発と嫌悪感
しかし、全てのインフルエンサーの効果が無くなったわけではありません。
今でも影響力があって、効果的なプロモーションをしてる人もいます。こういった現状をしっかり理解して、賢くインフルエンサーを活用することがおすすめです。
インフルエンサーマーケティングはなぜ意味ない?

SNSや広告施策で期待通りの反応が得られなかった場合、「インフルエンサーは意味ない」と感じる企業・個人は少なくありません。しかし、その背景には構造的な原因や誤解が潜んでいます。
よくある誤解と実態
インフルエンサー活用については、フォロワー数だけが判断基準になりがちです。それ以外にも見落としやすいポイントがあります。
- フォロワー数偏重
↳実際の反応率やエンゲージメントが低いアカウントを選定している - 購買導線の欠如
↳投稿内容から購入につながる仕組みが設計されていない - ターゲットとズレた起用
↳インフルエンサーのフォロワー層が顧客像と一致していない - KPIが曖昧
↳何をもって成功とするのか初めに定めていない
これらの誤解に基づいた施策設計では、効果が出にくく、結果として「意味ない」と感じることになります。
よくある失敗事例
下記は、インフルエンサー施策で失敗したケースの一例です。どんな構造的なズレがあるのかを把握することが重要です。
| ケース | 失敗内容 | 失敗の原因 |
|---|---|---|
| 大フォロワー起用の投稿で反応ゼロ | 投稿の反応(いいね・コメント)が少ない、CVも発生せず | エンゲージメント率が低く、フォロワーの関心度が高くなかった |
| 商材と不一致なジャンル選び | 生活系インフルエンサーにBtoB商材を紹介しても反響なし | フォロワー層と商材の顧客層がずれていた |
| KPI未設計でただ投稿依頼 | リーチや反応を計測せず、効果検証が不可能に | 評価指標と追跡手段がなく、改善ができなかった |
このような事例から、「意味ない」と感じてしまうのは、戦略やターゲティング、設計に抜けがある場合が多いことが分かります。

施策設計やKPIの見直し不足
効果を得るには、ただ起用するだけでは不十分です。投稿前後の設計が欠けていると、反応も成果も見えにくくなります。
- 目的未明確
↳ブランド認知向上、購入促進、新規顧客獲得などの目的が曖昧なまま施策を実施している - KPI未設定
↳リーチ数、クリック率、CVなどを具体的に数値化していない - 導線未整備
↳リンク設置、割引コード、LP設計などで購買行動を促していない - 成果追跡の欠如
↳トラッキングタグやアクセス解析を使っていない
設計段階で数値や導線、測定方法まできちんと組み込まれていないと、施策は空振りに終わることがあります。

インフルエンサーマーケティングの効果を最大化するには?

インフルエンサーマーケティングを使う時、その効果を最大限に引き出すために次の3つのポイントが大切です。
SNSの選定
SNSにはそれぞれ違う特徴やユーザー層があります。
効果的なマーケティングをするためには、自社の商品やサービスに一番合ったプラットフォームを選ぶことが大事です。例えば、見た目の魅力を前面に出す商品ならInstagramが適してるし、動画でのデモンストレーションが効果的な商品はYouTubeやTikTokがおすすめです。
インフルエンサーとの関係性
単にインフルエンサーにお願いするだけじゃなくて、キャンペーンの目的や内容について細かく調整しましょう。
インフルエンサーのフォロワー層とメッセージの一貫性を保つためにも、コンテンツの中身や投稿のタイミングなど、細かいところまですり合わせをしましょう。
効果測定/PDCAサイクル
キャンペーンの効果を数値で測定して、そのデータを基に次の計画を立てることが大切です。
効果測定をすることで、どの戦略が上手くいってるのか、どの部分を改善する必要があるのかが分かりやすくなります。必要に応じて、マーケティング代理店に頼んで専門的な分析をしてもらうのも一つの方法です。
【SNS別】インフルエンサーマーケティングの効果測定方法
インフルエンサーマーケティングの効果を測るやり方は、使うSNSによって違います。ここでは、主要な4つのSNS(TikTok、YouTube、X(旧:Twitter)、Instagram)ごとの効果測定方法について説明します。
TikTok
【主要な測定項目】
- 視聴回数
- いいね数
- コメント
「インサイト」機能を使えば、このデータを簡単にチェックできます。無料で使えるし、初期設定も簡単です。
TikTokのアルゴリズムはユーザーのエンゲージメントを重視してるから、これらの指標は動画がどれだけおすすめされるかを反映します。
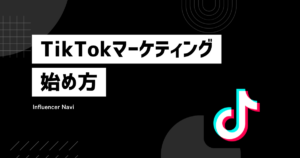
Youtube
【主要な測定項目】
- 視聴回数
- インプレッション数
- クリックスルーレート(CTR)
「YouTubeアナリティクス」を使えば、かなり詳しいデータが取れます。動画や広告のパフォーマンスを深く理解するのに役立つでしょう。
視聴回数とサムネイルのクリック率は、コンテンツがどれだけ魅力的か、ユーザーがどれだけ関心を持ってるかを示してください。あと、概要欄にリンクを貼れば、直接トラフィックや売上に繋げられます。

X(旧:Twitter)
【主要な測定項目】
- クリック率
- インプレッション数
- エンゲージメント数
「Xアナリティクス」を使えば、上記のようなデータを管理できるよ。数値的な分析ができるから、マーケティングの効果がはっきり分かります。
Xのダイナミックなプラットフォームでは、投稿がどれだけ目に留まるかが超重要です。ベストなタイミングで投稿すれば、最大のリーチとエンゲージメントを実現できるでしょう。
【主要な測定項目】
- リーチ数
- アクション実行数
- エンゲージメント数
「インサイト」機能を使えば、このデータをチェックできます。
大事なのは、Instagramでは拡散機能が限られてるから、エンゲージメント率がめちゃくちゃ重要です。エンゲージメント率が高いってことは、フォロワーがコンテンツにどれだけ関わってるかを示してて、それが直接的なコンバージョンに繋がります。

まとめ
この記事では、「インフルエンサーは意味ない」と感じてしまう背景や原因、そしてそれを乗り越えるための視点について整理しました。フォロワー数の多さだけで判断したり、購買導線の設計が不足していたりと、効果が出ないのには必ず理由があります。
一方で、適切な目的設定、KPIの設計、ターゲットとのマッチングがあれば、インフルエンサー施策は今でも非常に有効な選択肢になり得ます。
成功している事例の多くは、「誰に」「何を」「どう届けるか」を明確にし、それを測定・改善し続けている点に共通点があります。さらに、社員や顧客を活用したSNS施策、他チャネルとの連携といった代替案も検討することで、選択肢は広がります。